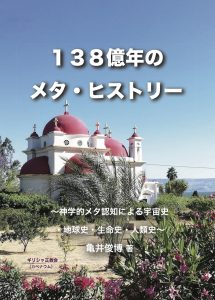写真:「金環蝕」2012年5月21日

亀井俊博(バイブル・ソムリエ)
「聖書を読む集い」牧師
「芦屋福音教会」名誉牧師
“人類哲学裏話し”
哲学者の裏話し
哲学(者)の裏話しです。
筆者は思想的なブログを書き連ねておりますので、長年結構色々な哲学・思想のお世話になっています。その実感として、何かとてつもなく難しい事を説いている論を読んでも、その核心は“なんだこの程度か、大げさな”と落胆する事が多い。高齢になると少々のこけおどしでは通用しない。それにしても大きな物語と言うか、新しい世界観を提示し、これからの人類や個人的にも道筋を照らすものがない。かつてフェミニズム論の上野千鶴子さんが、若い頃古代インド哲学にはまり、ありとあらゆる思考がそこに論じられていて、およそ人類の思考パタンはここに出尽くしていると悟り、哲学から方向転換したと書いていたのを思い出す。以後の人類の思考パタンは結局、古代インドの思考の焼き直しなのかもしれません。今は中国文明の台頭が大きいですが、どうも共産党の縛りが強いのか新しい哲学・思想はうかがえない。むしろ次の次に控えている、インドの熱帯雨林に繁茂する多様な植物の様な印度哲学・思想のジャングルの熱気の中から、次の世界思想が生まれてくる気がします。
日本の哲学
学生時代、文学部で哲学の講義を聴講、教師が本学で哲学の専攻者が学部・大学院あわせると100人以上いる。しかし哲学者がそんなにいるはずがない、と語っていた。結局哲学科を終了しても、西欧哲学の諸学説を理解するのが精いっぱい。とても独創的な哲学はそうそうは生まれないと言う事。そのためには高額な洋書を購入して読まなければならない。ある時京大哲学科出身の実業家と同席、どうして哲学を専攻しなかったのですか?と問うと、主任教授に院に進んで哲学を本格的に研究したいと相談。すると“君の家に蔵はいくつあるかね?”と聞かれた。いっぱしの哲学者になるには蔵の中の先祖のお宝を売って高額な洋書を購読しなければ無理だと言う事。彼は諦め別の道を進み成功したと言う。日本の哲学研究とは洋書の翻訳であったのですね。
筆者の長年の友人に某大学の哲学教師がおり、戦後京都学派哲学の重鎮 梅原猛の孫弟子でした。梅原の晩年一門が集まった時、師が“自分は西欧哲学を学び、さらに日本思想の独創性を解明する事を終え、学者人生の総仕上げに人類哲学を究明し、人類を救済する。”と大風呂敷を広げたそうです。会食の時、酔いが回った友人が梅原に“先生、わたしも人類哲学を考えています!”と話すと、喜んでくれるとか思いきや、とても嫌な顔をされた。梅原も度量が狭いとガッカリしたと友人は言う。友人はギリシャ哲学と中国哲学を研究し、東西融合の人類哲学を構築しようと目論んでいたからですが、大哲学者から見ると、何をこの若造が、まだ嘴(くちばし)が黄色い癖にと思ったのでしょうね。しかし梅原自身、京大哲学科で近世哲学の野田又夫教授の下で学んで、論文のテーマを決める時、日本哲学の研究をします、と野田に告げると、そんな事100年早い、日本人が西洋哲学を理解するのにはまだ100年はかかる、独創的な日本哲学などその後だ、と言う事だった。
“日本に哲学なし”と中江兆民は嘆いたが、戦前、独創的と言われた西田幾多郎・田辺元の京都学派哲学は、結局戦争加担の「近代の超克」思想として、戦後排除された苦い経験があったからでしょう。しかし、若い梅原は恩師の忠告に従わず、果敢に日本の独創的思想を現代によみがえらせ「梅原日本学」を確立し、さらに故中曽根首相に直談判し「国際日本文化研究センター」を設立、人材を輩出した。その彼が、後進の野心的な思想的挑戦をたしなめる。やはり歳取ると嫌味が出て後進をつまずかせる様になるのか、気を付けないといけないと、友の話を聞きながら自戒。
太陽の哲学・月の哲学
さて、梅原は晩年エジプト学者の吉村作治氏に誘われ、高齢を押してエジプトに赴き、古代エジプト文明の深淵さと壮大に魅了され研究。帰国後梅原のライフワーク、「人類哲学序説」(岩波新書)を世に問うた。ソムリエも当時興味深く読んだ。そこで展開されていたのは“太陽の哲学”であった。古代エジプトが太陽神ラーを生命の源として崇めた、今や科学技術の果てに人類滅亡の危機に直面している我々は、今こそ太陽の生命哲学を復帰させるべきだと、そもそも日本の古代神話の神“天照大神”は太陽神ではないか。太陽こそ洋の東西を問わず、全人類を照らす光明である。また太陽は地球上の全ての生命を愛しみ育てる。人間だけでなく全生物をあまねく照らす。そもそも人間中心の西洋哲学が、科学を使って地球環境を破壊している。これからは日本思想中でも日本天台仏教の独創である天台本覚思想“草木国土悉皆成仏”こそが、人類を滅亡から救うと言う、大風呂敷的哲学ですね。
筆者は哲学者ではありませんが、文学者の三島由紀夫の深い哲学的思想性を評価するものです。三島の到達点の遺作「豊饒の海」は、20歳で死んだ青年の愛と転生の物語りで、インドの輪廻転生論をベースに、仏教、神道、能と東洋思想を駆使した豊饒壮大な「世界解釈の小説」で彼独特の華麗な文体で酔わせます。しかし小説の最後は寺の庭に一陣の風が吹く、輪廻転生が終わり無明の業の世界から解脱した無(空)の世界が幕です。「豊饒の海」とは月面の一帯を指す地名です。「豊饒」と言うタイトルの生命の豊かさとは裏腹に、そこは死の静寂さの世界なのです。出版直後に彼はシンパを率いて自衛隊に突入、割腹して果てます。日本文化の極点は、月の文明、死の文明なのでしょう。月を愛でる室町以来の日本の美学に現れています。しかし、それは狭い日本にのみ通用し、いや精神の衰弱に過ぎないのではないか、これからの人類文明を救済するのは、月の哲学文明・死の哲学ではなく、太陽の哲学・生命文明なのではないか、と筆者は受け止め、老哲学者の白鳥の歌を感銘をもって拝読しました。
ビオスとゾーエー
しかし、ここからがキリスト教の出番です。聖書では生命には2種あります。新約聖書の原語ギリシャ語のビオスとゾーエーです。ビオスはバイオ・サイエンスの生命です。生物的生命、生老病死の生命です。梅原は人間中心で自然支配の西洋哲学は自然破壊をもたらし、日本天台本覚思想仏教の「草木国土悉皆成仏」こそこれからの人類哲学足り得ると説く。しかし筆者の研究によると、138億年前に誕生した宇宙の根本法則エントロピー増大の法則により、宇宙はやがて熱死する。しかしこれに抗い40億年前地球上に負のエントロピーにより死を免れようとする生命が誕生した(量子論物理学者、シュレジンガーの説)。生命の目的は永続です。しかしエントロピーの法則に生命もやがて負け、死滅する。いや太陽も月も被造物すべては死滅するのです。まさに仏教的無常の生命がビオスなのです。西洋哲学も梅原の日本哲学も無力なのです。
しかし、イエスは「わたしはよみがえりです。いのち(ゾーエー、永遠の生命)です。わたしを信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていてわたしを信じる者はみな、永遠に決して死ぬことがありません。あなたは、このことを信じますか。」(ヨハネ福音書11章25,26節)と、驚くべき事を宣言された。イエスだけがビオスの生命の限界を破って、十字架の死後、墓に葬られ、三日後に復活して、今も活きておられる永遠の生命(ゾーエー)なるお方なのです。
筆者は一昨年「138億年のメタヒストリー」を上梓しましたが、言うなれば聖書的「宇宙哲学」です。創造者なる神が万物を創造し、保持し、完成なさる壮大な宇宙論です。失礼ながら梅原の「人類哲学」でも神の知恵には到底及ばないのです。やはりここは聖書に哲学者も謙虚に耳を傾けるべきなのです。しかもその宇宙史の中心は、十字架にかかられ死んで、復活し今も全宇宙を統括されるイエス・キリストであると宣言する聖書こそは、哲学者は逆さになっても理解できない宇宙の秘儀なのです。
「天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、玉座であれ主権であれ権威であれ、御子にあって造られたからです。万物は御子によって造られ、御子のために造られました。」(コロサイ人への手紙、1章16節)。
三島文学・遠藤文学
三島の「豊饒の海」に対し、筆者はカソリック作家遠藤周作の「深い河」を対比しています。遠藤は明らかに三島を意識して書いています。三島が輪廻転生の時間的物語をオムニバス形式で描く様に、遠藤は独立した人生を同時並行的に歩む複数の人物が、オムニバス的に物語られ、最後にインド・ガンジス河で彼ら全員を遭わせます。そしてガンジスに身を浸して、人生を再生させる物語が、キリスト教の復活・新生の救済を東洋に土着化(インカルチュレーション)した文学表現で描くのです。映画化された最後のガンジスの沐浴シーンに観客は、涙で感動を現わしていましたね。ここに三島の到達点“無(空)”と、キリスト者遠藤の“復活”の違い、月の哲学と、復活の信仰、ビオスとゾーエーの命の差を思うべきでしょう。
要するに月も太陽もそれは被造物で創造者なる神ではなく、エントロピー法則を免れえない。究極的には死滅する。しかし、イエスだけは十字架上に人の罪とその報酬である死を滅ぼし、復活して永遠の生命(ゾーエー)をお持ちになる。彼を信じる者も罪赦され彼と共に死に、葬られるが、やがて復活し永遠の生命(ゾーエー)を持つ希望に生きている。哲学者は創造者なる父なる神、死に打ち勝つ救済者なる御子イエス・キリストを知らない。これからの人類哲学はこの永遠の命(ゾーエー)の賜物を求めるべきではないか。ここに年間100万人を超える大量死時代を迎えてた日本人の不安、ウクライナ戦争で核戦争の現実的危機に怯える世界、死の影のいよいよ濃くなった現代人への希望の哲学、いや福音がある。
「わたしはよみがえりです。いのち(ゾーエー、永遠の生命)です。わたしを信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていてわたしを信じる者はみな、永遠に決して死ぬことがありません。あなたは、このことを信じますか。」
(ヨハネ福音書11章25,26節)
(2025_4/30 ブログ、「バイブル・ソムリエ」 より)
ーーー
⬅️ クリック
ーーー
写真:「金環蝕」2912年5月21日
撮影場所:能勢川バイブルキャンプにて
撮影・提供:Shinichi Igusa