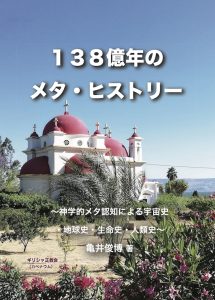写真:「さかい利晶の杜」茶室の庭

亀井俊博(バイブル・ソムリエ)
「聖書を読む集い」牧師
「芦屋福音教会」名誉牧師
“「日本文化の核心」ジャパン・スタイルを読み解く” を読む
松岡正剛の遺言的著作
ナルシストなのか、自分に自信がないのか、はたまた自己顕示欲が強いのか。日本人は日本人論が好きです。筆者も御多分に漏れず、その一人である事を認めます。数ある日本人論の白眉とも言うべき新刊書を紹介します。“「日本文化の核心」ジャパン・スタイルを読み解く”(松岡正剛、講談社現代新書)です。博覧強記の万能人、松岡正剛(1944~2024)の後世への遺言とも言うべき力作です。新書版ですが、「濃い日本」を解読する、と帯にありますが、よくまあコンパクトに濃厚な日本文化論を松岡は残してくれました。見事です。
日本人論の共通性
日本人論と言うと、本居宣長の「もののあはれ論」(1801)に始まり、「武士道」(1899)の新渡戸稲造、九鬼周造(1888)の「いきの構造」、恥の文化・罪の文化で有名なルース・ベネデイクトの「菊と刀」(1946)、「タテ社会の人間関係」(1967)の中根千枝、「甘えの構造」(1971)土居健郎、日本教・空気論で有名な「日本人とユダヤ人」(1971)山本七平、さらに巨視的な「文明の生態史観」(1957)梅棹忠夫・・が頭に浮かびます(「日本人論、再考」船曳建夫、日本放送出版協会、に詳しい)。これらは一つのキーワードで、二千年の日本史・日本文化の特徴を見事に取り出したもので、発表当時はもちろん、現在でも日本人の自己理解として定番の位置を占めています。
松岡の視点のユニークさ
しかし、松岡の日本文化論はそうではありません。日本文化の多様性、濃厚性を凝縮してではありますが、あらゆる時代・分野・テーマで論じているのです。時代性はホモ・サピエンスが2万年前に日本列島に棲みついて以来の先史時代・古代・中世・近世・近代から現代に至るまで。文化論としては、考古学、歴史学、宗教学、経済学、法学、文学・絵画・芸術論を始め狭義の文化論。分野は芸能(史)、和歌・歌謡・ポップス、雅楽・邦楽、武道・軍学・・筆者の様な狭い理解力では到底届かない、まさに森羅万象を熱く説く。しかも分かり易い表現ながら、厳密な語義・語源・歴史実証性の基礎の上に論じ圧倒されます。筆者のあやふやな知識が糺され、そういう意味だったのかと膝を打つ事多く。まさに“日本文化大全”の趣がこの小さな作品に凝縮しています。
それは、目次を見れば一目瞭然ですので、ここに記します。
第一講、柱を立てる(古代日本の共同体の原点「柱の文化」から話を始めよう)、第二講、和漢の境をまたぐ(「中国語のリミックス」で日本文化が花開いた)、第三講、イノリとミノリ(日本人にとって大切な「コメ信仰」をめぐる)、第四講、神と仏の習合(寛容なのか、無宗教なのか。「多神多仏」の不思議な国)、第五講、和する/荒ぶる(アマテラスとスサノオに始まる「和」の起源)、第六講、漂白と辺境(日本人はどうして「都落ち」に哀愁を感じるのか)、第七講、型・間・拍子(間と「五七」調の型と拍子にひそむ謎)、第八講、小さきもの(一寸法師からポケモンまで。「日本的ミニマリズム」の秘密)、第九講、まねび/まなび(世阿弥が説く学びの本質。現代日本の教育に足りないこと)、第一〇講、或るおおもと(公家・武家・家元。ブランドとしての「家」について)、第一一講、かぶいて候(いまの日本社会に足りない「バサラ」の心意気)、第一二講、市と庭(「庭」「お金」「支払い」に込められた日本社会の意外性)、第一三講、ナリフリかまう(「粋」と「いなせ」に見るコードとモードの文化)、第一四講、ニュースとお笑い(「いいね」文化の摩滅。情報の編集力を再考する)、第一五講、経世済民(日本を語るために、「経済」と「景気」のルーツをたどる)、第一六講、面影を編集する(一途で多様な日本、「微妙で截然とした日本」へ)。日本学大全ぶりが分かろうというものです。
JapanでなくJapans
ただ読後の印象として、「日本文化の核心」とは言うが、何が松岡文化論の主張なのか、甘えの構造、空気論・・これ一つで日本文化を読み解くマスターキーだと言うようなキーワードがない。いやむしろ松岡はそのような方法論の危険性を説く。ジョン・ダワーが「実を言うと、『日本』でさえ存在しません。逆に、私たちが語らねばならないのは、『日本文化たちJapanese cultures』であり、『日本の伝統たちJapanese traditions』なのです。私たちは、『日本たち』 Japansと言うべきなのです」(「敗北を抱きしめて」J.ダワー)を松岡は忠実に採用しています。日本を複合的に捉えると言う事です。そこに本書の奥深さ、日本文化の複雑で複合的な重層性の分厚さ豊饒性をくみ取ることができます。
「面影」による日本文化編集
しかしそれだけでは、日本文化を羅列しただけになります。松岡はそんな乱暴な事はしません。彼独自の方法論「編集工学」、世界はそのままでは認知・理解できない。人間は生の世界を、編集してこそ認知・理解可能になる、との方針によって複合的日本文化を彼独自の方法で編集して見せたのです。その独自な方法が「面影」的歴史理解です。松岡は言う“バックミラーに移る日本の歴史文化をちらちら眺めながら、目前のコンビニやアニメやテレビ番組でおこっていることを見るのがいい”と。お笑い芸人や、アニソンを楽しみ(後期高齢の筆者にはついていけない事が多いが!)ながら、彼らの背後に、長く重層的な日本文化が今・ここに・この表現で現出していると観る、と言う事。
読後感想
(1)面影の編集、日本文化観
感想、ポップカルチャーを歴史から切り離すのでなく、それを日本の文化の豊かな歴史の過去から「面影」を思い出すとき、文化の連続性がポップスにあり、また新しい創造性も見ることができる、“日本文化の特色は「面影を編集する」ところにある。日本人は記憶の中の面影を情報化し、そこに編集を加えていった。和歌も能もそのようにして生まれ、俳諧も浮世絵もそのようにして生まれ、溝口健二や藤沢周平はそのような面影を映画や小説にし、美空ひばりや井上陽水はそうした面影をうたっていったのです。”と松岡はしみじみ述べる。松岡の懐の深さ、共感力の豊かさに感嘆します。
(2)歴史とは思い出
ただこういう事も言えるのではないでしょうか。「面影」とは何か?かつて小林秀雄が「歴史とは畢竟(ひっきょう)思い出である」と語ったのに通底しないかと言う事です。われわれは歴史が何かある理念、それが「神の国」や「ユートピア」、「自由な市民社会」、「共産主義社会」等の実現のどれであるかは別にして、理念の実現の方向に向かっている。その実現に様々な困難や戦いを克服して今を生きる希望とする、と言うような歴史観や人生観を持っていない。
何か人生や社会に問題が起こると、自分や社会歴史の過去の思い出を探り、ああ昔にもよく似たことがあったなあ、あの時はああして対処したから今回も同様で行こうと考えると、上手に思い出す事、それが歴史だと小林は語ったのでしょうか。確か山本七平は日本文化の“掘り起こし共鳴現象”と呼んでいました。外来の新しい文化が到来すると、日本人は過去のよく似た事象を思い出し、そうかあれのニュー・バージョンなんだなと納得し安心する、という現象です。そもそもこういう理解の仕方が実例ですね。そこを取り上げて松岡は「面影」で勝負する。過去の遺産を取り出しそれに現代的工夫を施して対応する。日本得意のカイゼンですね。
(3)聖書的創造性を
それは今まではよかった。しかし、この世界的地盤が激変する時代に在って、他文化・他文明の発する強烈な理念思考に対処できるのか。ロシヤのプーチン、アメリカのトランプ、中国の習近平の、現状破壊と彼らの説く、新しい世界秩序に右往左往してあたふた対症療法的対応に苦慮する我々の姿。いや対応、対処と言う方法そのものが「思い出」「面影」に依存する過去指向ではないか。世界には未来的創造的な、さらには現状破壊的な、人間や社会が存在しているのです。そしてその新しい理念への対応を「思い出」「面影」で処するのは衰退の道しかありませんよ。
万学の巨人の松岡正剛の遺言的名作に深く学びつつ、別な道を求める必要を痛感します。それは日本人が、聖書を読み神の壮大な宇宙・生命・人類の創造と堕落・救済と完成の物語(拙著、「138億年のメタ・ヒストリー」はその試論)に触れてこそ成しうる事だと信じます。
「見よ、わたしは新しいこと行う。今、それが芽生えている。あなたがたはそれを知らないのか。必ず、わたしは荒野に道を、荒れ地に川を設ける。」 (イザヤ書43:19)
(2025・7・2、ブログ “バイブル・ソムリエ”より)
ーーー
https://amzn.to/3JAn1cG https://amzn.to/47Dsmbi
*写真:「さかい利晶の杜」茶室の庭
2016-11/25 @ Shinichi Igusa
ーーー