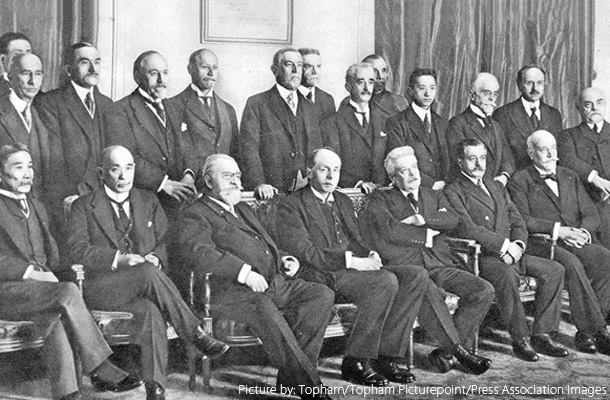中川晴久
東京キリスト教神学研究所幹事
日本基督神学院院長
SALTY-論説委員
<はじめに>
倉山満著『ウッドロー・ウィルソン』には、「全世界を不幸にした大悪魔」という副題がついています。
・かつて私はこんな問いを投げかけられたことがあります。
「〈オレは悪魔だ。〉という人間と〈オレはキリストだ。〉という人間のどちらが悪魔だろうか?」と。
・当時の私はどっちもどっちだと思って返答できませんでした。みなさんなら何と答えるでしょう。もちろん二者択一の答えなどないわけです。子供の頃に同級生のやんちゃな友達が「オレは〇〇だ!」と言っていた中に、「悪魔だ!」「神だ!」もあったでしょう。自分でもそんなことを言ったことが一度や二度あるかもしれません。でも、現実がちゃんとこれを否定し矯正してくれるものです。しかし、大人になっても「オレは悪魔だ。」「オレはキリストだ。」と本気で信じている人がいたとしたら、どうでしょう。
・この『ウッドロー・ウィルソン』を読むと、この問答の正解が差し出されているようにも思えてくるのです。
<ウッドロー・ウィルソン>
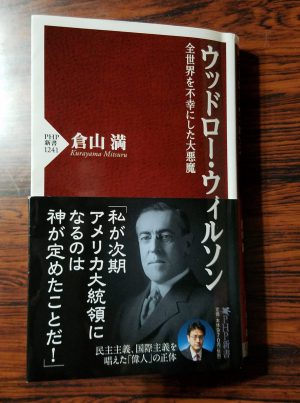
・ウィルソン(1856年12月28日 – 1924年2月3日)といえば、第一次世界大戦の講和会議で国際連盟設立を提唱し、その基礎となった「ウィルソンの十四ヵ条」を発表して、「平和の理念」を高らかに掲げた米国大統領として教えられたことがあります。ウィルソンがこの「平和の理念」を米国に持ち帰ると、当時の米国議会はこれに反対し国際連盟に参加できず、米国抜きの脆弱な国際連盟は国際秩序を維持するだけの力を持てなかったため、ウィルソンの理念が瓦解したと、私は理解していました。皆さんにあっても、おおかたウィルソンの名前を聞くとそんなことが思い浮かぶのではないでしょうか。
<ウィルソン誕生>
・トマス・ウッドロー・ウィルソンは、北アイルランドからの移民3代目で米国の主流である、いわばWASP(ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント)と呼ばれる人たちに属します。父ジョセフ・ウィルソンは、バージニア州の第一長老派の牧師でした。ジョセフは息子が生まれると間もなく、一家でジョージア州に移ります。ちょうど南北戦争が始まろうとしているときで、ウィルソンが生まれた1850年代が最も激化しました。父ジョセフは、このとき南軍において従軍牧師を務めています。
・ウィルソンはかなり信仰的な家庭で育つことになります。特に南北戦争のさなか、礼拝や祈祷会に通い、家庭ではしっかりと聖書を読むことを日課として過ごす牧師家庭です。そんな中で、「ひとりでに意識を失う奇妙な癖をもっていた」ようです。
空想がちで信仰復興運動にのめり込む十代半ばを過ごしたトマスは、1873年のある日「わたしの心に神の恩寵のしるしが現れはじめた」と告白するのです。人類史上最大の「中二病」が発病しました。p.30.
<自分の理想を実現させる優れた知能>

・ウィルソンは、現実の前に観念が先行していました。大学で弁論部に入ると、イギリス衆議院の雄弁家グラッドストンに自分が似ていると思い込んだ節があり、さらに自分の卓越した能力を活かして人びとを導きたいと大志を抱いてしまったようです。思春期であれば、多少の思い込みや勢いが高じても、誰もが温かく見守るでしょう。どうやらウィルソンはその許容を越えていたようです。
・グラッドストンを自分に重ね、ウィルソンはバージニア州選出上院議員の名刺を自作して所持してしまいました。後に、ニュージャージー州知事となり、現実のものとしていきます。
・また1882年6月には弁護士事務所を友人と設立します。この時、まだ弁護士資格はありません。しかしその持ち前の頭の良さで10月には見事に弁護士資格を取得します。こっちも時系列が逆です。
・その後には、ジョンズ・ポプキンス大学の大学院に進学し、議会を一度も見ずに『議会政治』の論文を書き上げ、博士号が授与されます。さらには、プリンストン大学で教鞭をとるようになり、45歳の若さでプリンストン大学の学長に就任してしまうのです。
<世界の舞台へ>
・ウィルソンは「観念先行主義です。」が、それを実現化する頭脳があり、さらにそこに権力も持つことになっていきます。以上のように超人的に頭の良い人間が信仰と正義に裏打ちされて米国大統領になり、第一次世界大戦の非常に不安定な世界の秩序に対して諸国一致して協調をもって取り組んでいこうという舞台を与えられてしまうとどうなるか。
・もちろん、信仰と正義といっても、それはあくまでもウィルソン個人の信仰であり正義です。
<第4章、第5章から読むのをお勧め>
・ウィルソンの謳った「民族自決」は本当に正しいことであったのか、また「十四ヵ条の宣言」がもたらした人類の災厄はいかなるものであったか。
なぜ米国議会はウィルソンの持って帰ってきた国際連盟の加入を拒否したか。
・この本『ウッドロー・ウィルソン』は第4章と第5章から読んでいくことをお勧めします。たいてい各章の見出しのタイトルは出版社の手によるものなのではないかと思うのですが、そうだとしても見事です。以下のようになっています。
第4章
十四ヵ条の平和原則ーかくして人類は地獄に突き落とされた
第5章
パリ講和会議とその後ーなぜ全世界が不幸になったのか
・この2つの章をまず先に読んで、改めて最初から読み進めてみると、このようなウィルソンという人物がなぜ世界の舞台に立ってしまったのかを、そのアイデンティティの構築を追って読み進めることができるので、興味深く読めると思います。とくに、キリスト者はウィルソンの信仰と現実への適用という視点からも見れるので、その危険がどうもリアルな目の前の現実としても読めるでしょう。
<わたしの感想>
・ウィルソンの提言した「民族自決」や「十四ヵ条の平和宣言」がいかなる結果を生んだかは、ここでは述べません。ネタばらしは避けたいということもあるし、この本を実際にぜひ手に取って読んで頂きたいからでもあります。
・倉山満著『ウッドロー・ウィルソン』「全世界を不幸にした大悪魔」を読んでいる間、何度も繰り返し思い浮かんだことはヨーロッパのことわざです。
「地獄への道は善意で舗装されている」
・ウィルソンと同じく私も保守的な福音派の信仰を持っています。だから、彼の滑りやすさが分かるような気がするのです。おそらく「理念」「正義」「正しさ」に突き進む彼には、他に選択肢がなかったでしょう。【神にあって妥協などあり得ない】という心理を分かってしまうのが、私自身恐ろしくもあります。というのも、著者の倉山満氏にあって、それは「狂人」と表現されるところのものだからです。もちろん、私としては自分は「狂人」となる一線は越えるはずもないと自己認識しているのですが・・・。
・とはいえ「正義であれば、本当にそれは正しいのか?」という矛盾した疑問を、私はこれまでの信仰生活の中で何度も考えさせられました。立ち止まる状況がたくさんあったということで、それは滑りやすい道を歩んでいるからだとも言えます。
・信仰者の目から「(キリスト教的)正義」であっても、信仰者でない人たちからは「正義」ではないことなど、いくらでもあるわけです。事実、キリスト教の歴史を少しでも概観すれば、教派的な教義による合理性が生み出した「正しさ」が、信仰に裏打ちされて起きた独善的な行為がたくさんあり、そこから生まれる対立や失敗が繰り返し起こっています。もっと時代考証される必要はあるとはいえ、魔女裁判や十字軍、植民地主義などはよく挙げられる事例です。ここであえて言えば、今後問われるべき問題としてキリスト教的正義からくるキリスト者の「文化破壊への意識」をとりあげたいです。ただ、これについては改めて別の紙面を持たねばなりません。
・「神への信仰」にあって選ばれ「神の正義」をうち立てると思い込んでいる人間、つまり「私はキリストだ。」というような人間は、悪魔的な結果を生むということは確かなようです。